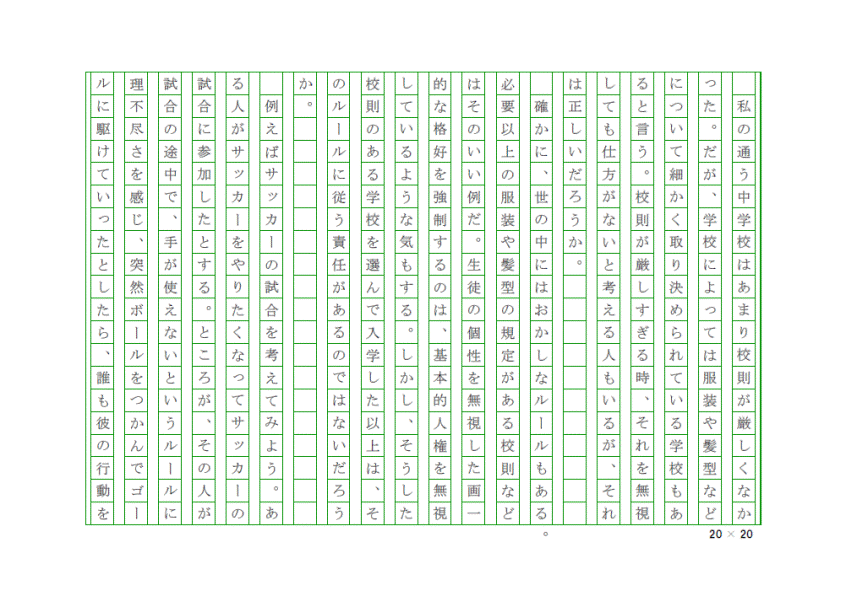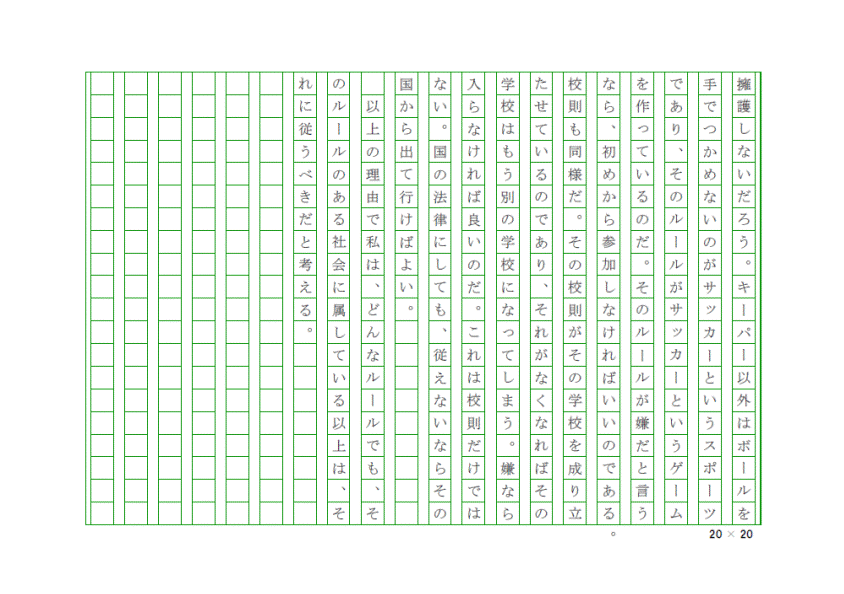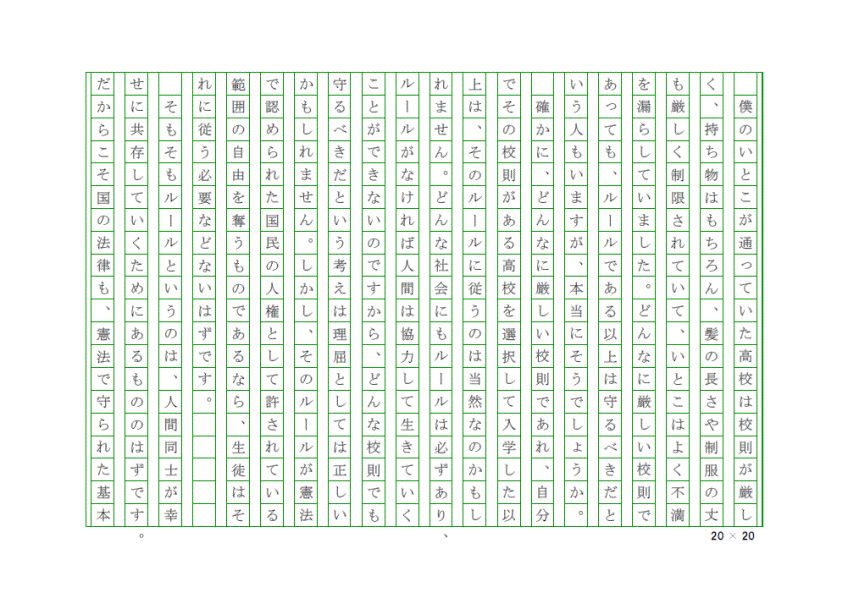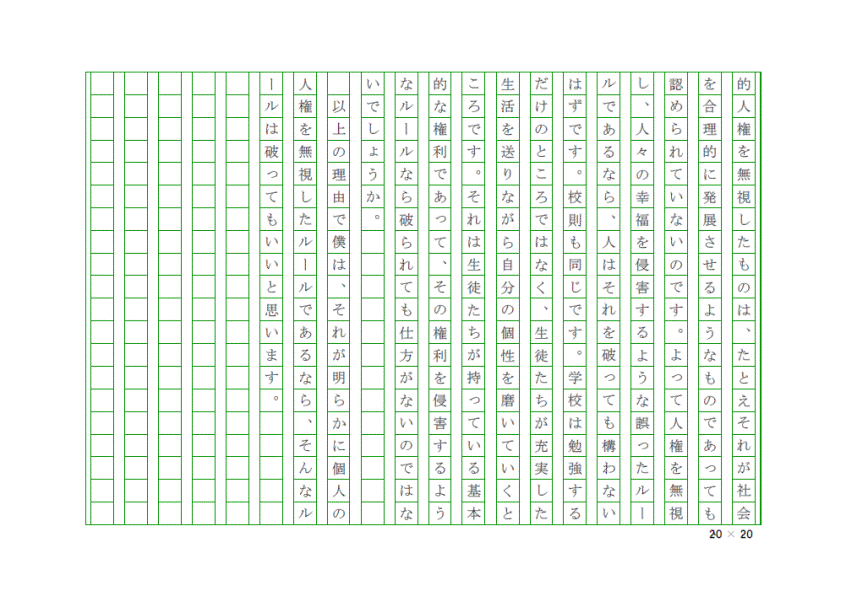|
小論文例文集 このページは中高生のための小論文の例文集です。 この≪小論文講座≫に挙げられた例文は、全て小論文指導の大家である樋口裕一先生の説く4段落構成の「型」にはめて書かれた文章になっています。 文章はまず、テンプレートを使って練習しましょう。小論文には様々な「型」がありますが、一つでもいいので「型」を覚えないことには、ゼロのままです。型のない、自由で個性的な文章というものはありません。それは、文法が全くない言語を話すようなもので、おそらく誰にも理解することが出来ない文章になるでしょう。 小論文の例文を読む前に、まずは「型」を確認しましょう。 1回目は、「ルールを守る」です。 |
|
|
|
問題 「ルールを守る」ことについて、校則・交通規則など身近な例を挙げながらあなたの考えを述べなさい。 (600字〜800字) 序論 [一段落目] 話題の導入&問題提起 一段落目では、これから自分がどんな事柄について話を進めていくのか、読む人へ話題を示します。そして、その話題に関して自分が抱いた疑問を問題として提起します。 今回は「ルールを守る」なので、身近なところで学校の校則に関わるニュースや世間話などを話題に挙げてみましょう。地毛の茶色いハーフの生徒に対して黒髪に染めるよう強制した学校などがあって、厳しすぎる校則やちょっと変な校則が世間で話題になることがあるので、とりあえずその辺りを話題に出すとします。すると、問題提起としては、そういう校則や学校に反感を持っているなら、「このようなおかしな校則でも守らなければならないのだろうか」といった文章が考えられますし、「ルールはルールだ守ろうぜ!」と考える立場なら、「おかしな校則なら違反してもいいと言う人もいるが本当にそうだろうか」と書いてみてもいいでしょう。 大事なのは、どのような問題提起になっているかを読むだけで、その後の主張が「肯定」と「否定」のどっちの立場に立つものなのか予想できた方が、文章として整っていて、読み手に親切だということです。「こんなルールに従うべきだろうか」と言っておきながら結論は「従うべきだろ」だったり、「ルールを破ってもいいのだろうか」と言いながら「破ってもいいんだよ」とまとめたりすると、「どっちなんだよ!」とつっこまれることになり、意見としてチグハグな印象を与えてしまいます。 というわけで、問題提起は自分の結論をきちんと固めてから作るようにしてください。あるいは、問題提起の感情に沿った約束通りの結論を書くようにしてください。意外な結論は、かなり文才のある人しか成功しません。よって今このサンプルを読んで小論文の書き方を知ろうとしているあなたでは、意外な結論などまだ書けないということです。 展開が予想できる文章を書くことのできない人には、展開が予想できない文章ではなく、展開が滅茶苦茶な文章しか書けませんよ。 本論 [二段落目] 対立する意見への譲歩&自分の意見の提示 樋口先生の小論文と言えば本論を二つの形式段落に分ける修辞技法を使うことで有名ですが、中でも特徴的なのがこの二段落目です。「確かに、」の書き出しで自分と対立する意見に対し部分的にその正しさをいったん認めながら、「しかし、」と続けて自分の意見を提示します。 この二段落目できちんと「自分の主張」と「想定できる反論」を読む人に示し、比較・検証してもらえるかどうかが、この修辞法のキーになります。どんな主張を展開したくても、自分に対立する意見にも正義があることを認めなければ、公平な意見には見えず、公平にものを見ようとする読者に対しては説得力を持ちません。客観的にものを考える訓練にもなるので、ぜひ身につけてもらいたい形式なのですが、実のところかなり高度で失敗しやすい修辞法でもあります。「確かに、」と書き出した自分と対立する意見の正しい部分を並べているうちに、いつの間にかそっちの方が本当に正しく思えてきて、「しかし、」が言えなくなってしまうなんてこともありがちです。時間をかけてよいので、対立意見と自分の意見をメモしたりして並べ、比較しながら、最終的には自分の気持ち・感情に沿った形式になるように文章を考えましょう。 慣れてきた人や器用な人だと、「どっちでも書けそうだな・・・」と思えてくるかもしれません。そうしたら、実際に相対立する意見の小論文をゲーム感覚で二つ書いてみてもいいでしょう。きっと書き上げる前より視野が広がるはずです。 [三段落目] 意見の展開(自説の根拠・理由) 本論の二つ目にして、文章全体の中でクライマックスに当たる段落です。[二段落目]で提示した自分の意見の根拠・理由となるネタを読者に開陳しなければなりません。本やテレビ、インターネットで得た知識を基に論理を展開していったり、自分の実体験を基に感じたこと・考えたことを述べたりして、読む人に「なるほど、そう言われるとそうかもしれないなぁー」と思わせましょう。 体験と言いましたが、実際にはそれに見せかけたリアルなウソや、人から聞いた物語でも構いません。とにもかくにも、「なるほどねー」と思わせられたらあなたの勝ちです。 [四段落目] 文章の締め・まとめ [二段落目]と[三段落目]の本論で言いたいことが言いきれたとしても、読者に対して最後の挨拶は必要です。とりあえず慣れないうちは「以上の理由で私は〜と考える」と書いておけば、挨拶としては無難でしょう。 慣れてきた人や言葉の上手い人は、いろいろとドラマの最後にふさわしい決め台詞を工夫してみてください。本論で説得力のある文章を書けたとしても、ラストがカッコ良くないと、読む人に余韻を残せません。ここまできたら最期まで形式美を追求したほうが、ゲームとしても楽しいですよ。 例文1 <肯定派> (話題の導入)私の通う中学校はあまり校則が厳しくなかった。だが、学校によっては服装や髪型などについて細かく取り決められている学校もあると言う。(問題提起)校則が厳しすぎる時、それを無視しても仕方がないと考える人もいるが、それは正しいだろうか。 確かに、世の中にはおかしなルールもある。必要以上の服装や髪型の規定がある校則などはそのいい例だ。生徒の個性を無視した画一的な格好を強制するのは、基本的人権を無視しているような気もする。しかし、そうした校則のある学校を選んで入学した以上は、そのルールに従う責任があるのではないだろうか。 例えばサッカーの試合を考えてみよう。ある人がサッカーをやりたくなってサッカーの試合に参加したとする。ところが、その人が試合の途中で、手が使えないというルールに理不尽さを感じ、突然ボールをつかんでゴールに駆けていったとしたら、誰も彼の行動を擁護しないだろう。キーパー以外はボールを手でつかめないのがサッカーというスポーツであり、そのルールがサッカーというゲームを作っているのだ。そのルールが嫌だと言うなら、初めから参加しなければいいのである。校則も同様だ。その校則がその学校を成り立たせているのであり、それがなくなればその学校はもう別の学校になってしまう。嫌なら入らなければ良いのだ。これは校則だけではない。国の法律にしても、従えないならその国から出て行けばよい。 以上の理由で私は、どんなルールでも、そのルールのある社会に属している以上は、それに従うべきだと考える。 例文2 <否定派> (話題の導入)僕のいとこが通っていた高校は校則が厳しく、持ち物はもちろん、髪の長さや制服の丈も厳しく制限されていて、いとこはよく不満を漏らしていました。(問題提起)どんなに厳しい校則であっても、ルールである以上は守るべきだという人もいますが、本当にそうでしょうか。」 確かに、どんなに厳しい校則であれ、自分でその校則がある高校を選択して入学した以上は、そのルールに従うのは当然なのかもしれません。どんな社会にもルールは必ずあり、ルールがなければ人間は協力して生きていくことができないのですから、どんな校則でも守るべきだという考えは理屈としては正しいかもしれません。しかし、そのルールが憲法で認められた国民の人権として許されている範囲の自由を奪うものであるなら、生徒はそれに従う必要などないはずです。 そもそもルールというのは、人間同士が幸せに共存していくためにあるもののはずです。だからこそ国の法律も、憲法で守られた基本的人権を無視したものは、たとえそれが社会を合理的に発展させるようなものであっても、認められていないのです。よって人権を無視し、人々の幸福を侵害するような誤ったルールであるなら、人はそれを破っても構わないはずです。校則も同じです。学校は勉強するだけのところではなく、生徒たちが充実した生活を送りながら自分の個性を磨いていくところです。それは生徒たちが持っている基本的な権利であって、その権利を侵害するようなルールなら破られても仕方がないのではないでしょうか。 以上の理由で僕は、それが明らかに個人の人権を無視したルールであるなら、そんなルールは破ってもいいと思います。 |
|
|
|
例文1 <肯定派>
例文2 <否定派>
|