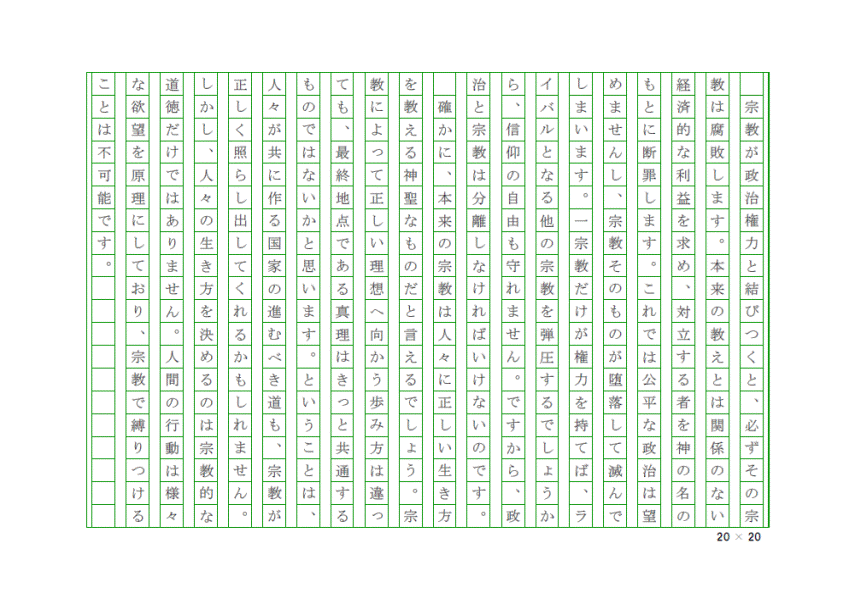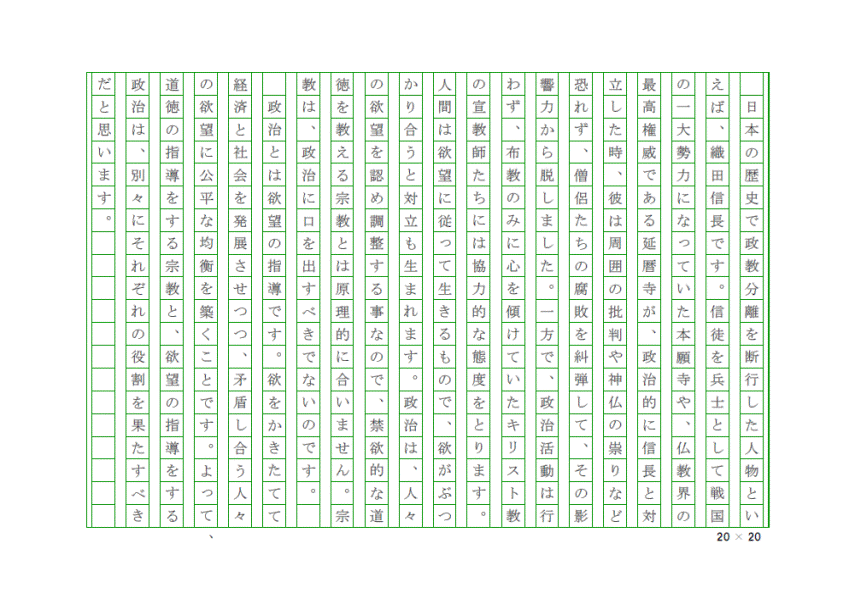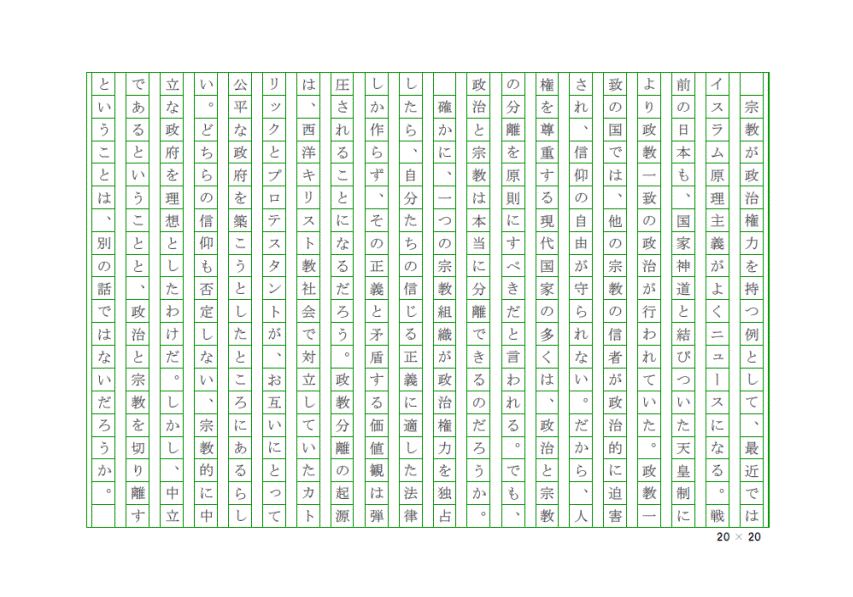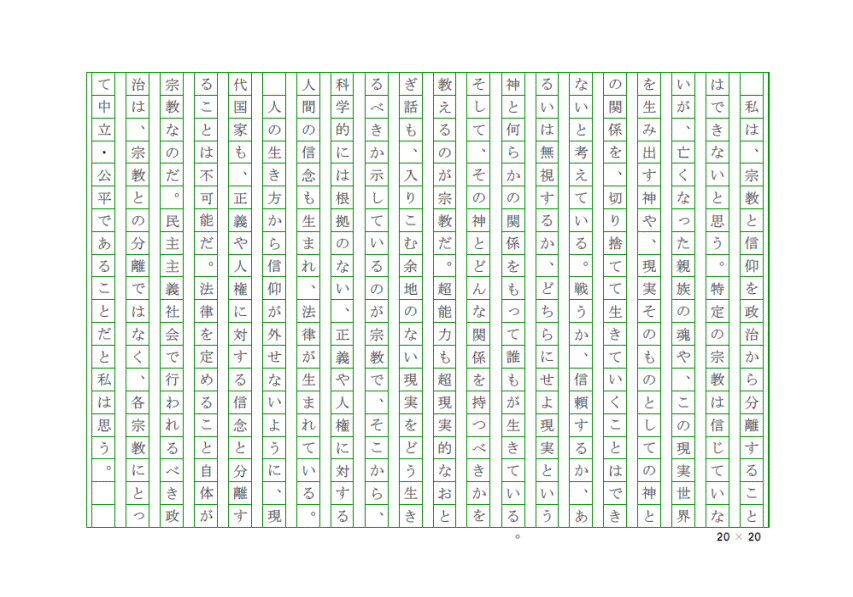|
小論文例文集 このページは中高生のための小論文の例文集です。 8回目は、「政教分離」です。 |
|
|
|
問題 「政教分離」という考え方について、まず肯定か否定かを述べ、自分の意見に説得力を持たせるための根拠とその根拠を支える具体的な例をあげながら、自分の意見を論理的に述べなさい。 (600字〜800字) 参考記事 序論 [一段落目] 話題の導入&問題提起 本論 [二段落目] 対立する意見への譲歩&自分の意見の提示 [三段落目] 意見の展開(自説の根拠・理由) [四段落目] 文章の締め・まとめ 例文1 <政教分離 肯定派> 宗教が政治権力と結びつくと、必ずその宗教は腐敗します。本来の教えとは関係のない経済的な利益を求め、対立する者を神の名のもとに断罪します。これでは公平な政治は望めませんし、宗教そのものが堕落して滅んでしまいます。一宗教だけが権力を持てば、ライバルとなる他の宗教を弾圧するでしょうから、信仰の自由も守れません。ですから、政治と宗教は分離しなければいけないのです。 確かに、本来の宗教は人々に正しい生き方を教える神聖なものだと言えるでしょう。宗教によって正しい理想へ向かう進み方は違っても、最終地点である真理はきっと共通するものではないかと思います。ということは、人々が共に作る国家の進むべき道も、宗教が正しく照らし出してくれるかもしれません。しかし、人々の生き方を決めるのは宗教的な道徳だけではありません。人間の行動は様々な欲望を原理にしており、宗教で縛りつけることは不可能です。 日本で政教分離を断行した歴史上の有名人といえば、織田信長です。信徒を兵士として戦国の一大勢力になっていた本願寺や、仏教界の最高権威である延暦寺が、政治的に信長と対立した時、彼は周囲の批判や神仏の祟りなど恐れず、僧侶たちの腐敗と堕落を糾弾し、真正面から戦いました。一方で、政治活動は行わず、布教のみに心を傾けていたキリスト教の宣教師たちには協力的な態度をとっています。人間は欲望に従って生きるもので、欲がぶつかり合うと対立も生まれます。国の政治は、人々の欲を認めてそれを調節する事であり、禁欲的な道徳を教える宗教とは原理的に合わないため、宗教は政治に口を出すべきでないのです。 政治とは欲望の指導です。欲をかきたてて経済と社会を発展させつつ、矛盾し合う人々の欲望に公平な均衡を与えるものです。よって、道徳の指導をする宗教と、欲望の指導をする政治は、別々にそれぞれの役割を果たすべきだと思います。 例文2<政教分離 否定派> 宗教が政治権力を持つ例として、最近ではイスラム原理主義がよくニュースになる。戦前の日本も、国家神道と結びついた天皇制により政教一致の政治が行われていた。政教一致の国では、他の宗教の信者が政治的に迫害され、信仰の自由が守られない。だから、人権を尊重する現代国家の多くは、政治と宗教の分離を原則にすべきだと言われる。でも、政治と宗教は本当に分離できるものだろうか。 確かに、一つの宗教組織が政治権力を独占したら、自分たちの信じる正義に適した法律しか作らず、その正義と矛盾する価値観は弾圧されることになるだろう。政教分離の起源は、西洋キリスト教社会で対立していたカトリックとプロテスタントが、お互いにとって公平な政府を築こうとしたところにあるらしい。どちらの信仰も否定しない、宗教的に中立な政府を理想としたわけだ。しかし、中立であるということと、政治と宗教を切り離すということは、別の話ではないだろうか。 そもそも宗教と信仰を政治から分離することなどできない。私は特定の宗教を信じているわけではない。でも、亡くなった親族の魂や、私を取り巻く現実世界を生み出す神、あるいは現実そのものとしての神との関係を、切り捨てて生きていくことはできないと考えている。戦うか、信頼するか、あるいは無視するか、どちらにせよ、現実という神といずれかの関係をもって誰もが生きている。そして、その神とどんな関係を持つべきかを教えるのが宗教だ。超能力も超現実的なおとぎ話も、入りこむ余地がない現実をどう生きるべきか示すのが宗教で、そこから、科学的には根拠のない、正義や人権に対する人間の信念が生まれ、法律が生まれる。 人の生き方から信仰が外せないように、人間の国家も、正義や人権に対する信念と分離した法を定めることは不可能だ。なぜなら、法律を定めること自体が宗教だからだ。民主主義社会で行われるべき政治は、宗教との分離ではなく、各宗教にとって中立・公平であることだと私は思う。 |
|
|
|
例文1 <政教分離 肯定派>
例文2<政教分離 否定派>
|