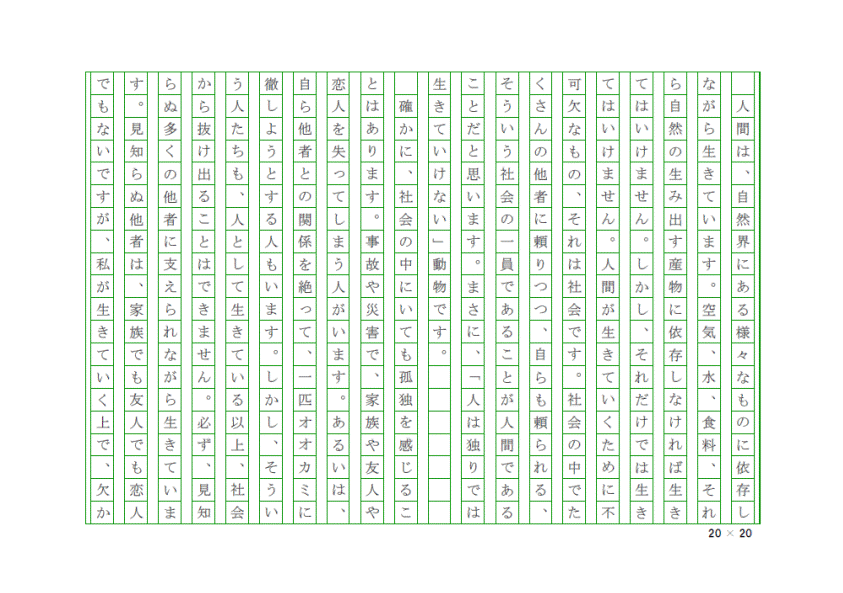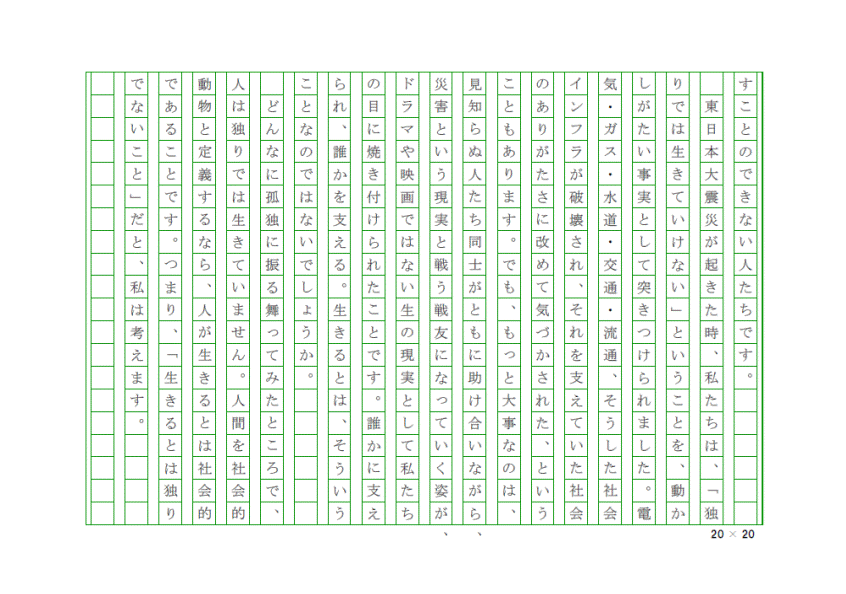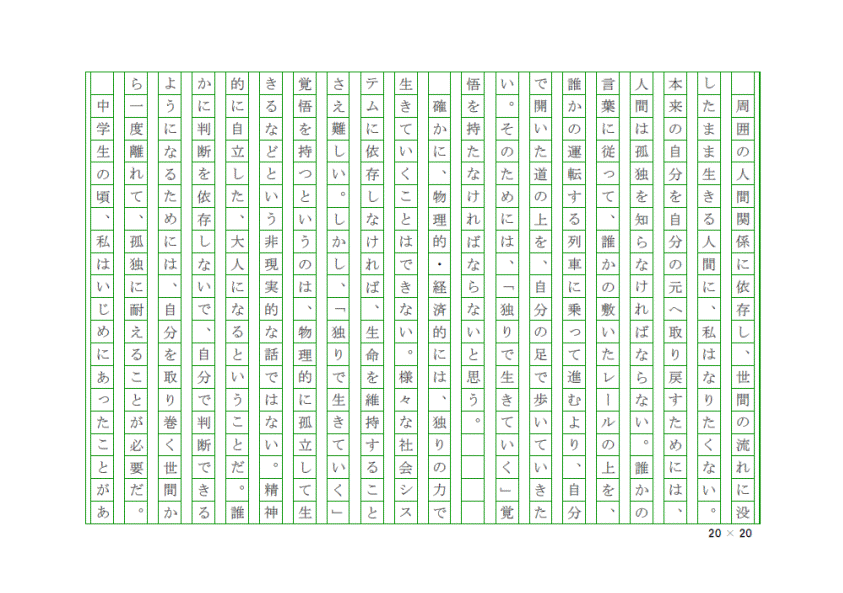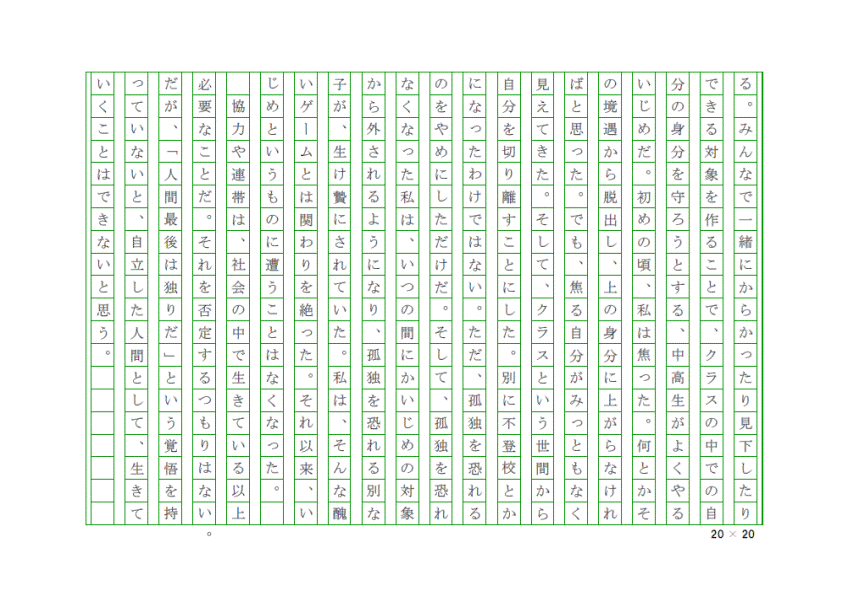|
問題
「人は独りでは生きていけない」という考え方について、肯定か否定かどちらかの立場に立ち、具体的な例をあげながらその理由を説明し、自分の意見を論理的に述べよ。(600字〜800字)
序論
[一段落目] 話題の導入&問題提起
本論
[二段落目] 対立する意見への譲歩&自分の意見の提示
[三段落目] 意見の展開(自説の根拠・理由)
結論
[四段落目] 文章の締め・まとめ
例文1 <人は独りでは生きていけない 肯定派>
人間は、自然界にある様々なものに依存しながら生きています。空気、水、食料、それら自然の生み出す産物に依存しなければ生きてはいけません。しかし、それだけでは生きてはいけません。人間が生きていくために不可欠なもの、それは社会です。社会の中でたくさんの他者に頼りつつ、自らも頼られる、そういう社会の一員であることが人間であることだと思います。まさに、「人は独りでは生きていけない」動物です。
確かに、社会の中にいても孤独を感じることはあります。事故や災害で、家族や友人や恋人を失ってしまう人がいます。あるいは、自ら他者との関係を絶って、一匹オオカミに徹しようとする人もいます。しかし、そういう人たちも、人として生きている以上、社会から抜け出ることはできません。必ず、見知らぬ多くの他者に支えられながら生きています。見知らぬ他者は、家族でも友人でも恋人でもないですが、私が生きていく上で、欠かすことのできない人たちです。
東日本大震災が起きた時、私たちは、「独りでは生きていけない」ということを、動かしがたい事実として突きつけられました。電気・ガス・水道・交通・流通、そうした社会インフラが破壊され、それを支えていた社会のありがたさに改めて気づかされた、ということもあります。でも、もっと大事なのは、見知らぬ人たち同士がともに助け合いながら、災害という現実と戦う戦友になっていく姿が、ドラマや映画ではない生の現実として私たちの目に焼き付けられたことです。誰かに支えられ、誰かを支える。生きるとは、そういうことなのではないでしょうか。
どんなに孤独に振る舞ってみたところで、人は独りでは生きていません。人間を社会的動物と定義するなら、人が生きるとは社会的であることです。つまり、「生きるとは独りでないこと」だと、私は考えます。
例文2<人は独りでは生きていけない 否定派>
周囲の人間関係に依存し、世間の流れに没したまま生きる人間に、私はなりたくない。本来の自分を自分の元へ取り戻すためには、人間は孤独を知らなければならない。誰かの言葉に従って、誰かの敷いたレールの上を、誰かの運転する列車に乗って進むより、自分で開いた道の上を、自分の足で歩いていきたい。そのためには、「独りで生きていく」覚悟を持たなければならないと思う。
確かに、物理的・経済的には、独りの力で生きていくことはできない。様々な社会システムに依存しなければ、生命活動を維持することさえ難しい。しかし、「独りで生きていく」覚悟を持つということは、物理的に孤立して生きるなどという非現実的な話のことではない。精神的に自立した、大人になるということだ。誰かに判断を依存しないで、自分で判断できるようになるためには、自分を取り巻く世間から一度脱却し、孤独に耐えることが必要だ。
中学生の頃、私はいじめにあったことがある。みんなで一緒にからかったり見下したりできる対象を作ることで、クラスの中での自分の身分を守ろうとする、中高生がよくやるいじめだ。初めの頃、私は焦った。何とかその境遇から脱出し、上の身分に上がらなければと思った。でも、焦る自分がみっともなく見えてきた。そして、クラスという世間から自分を切り離すことにした。別に不登校とかになったわけではない。ただ、孤独を恐れるのをやめにしただけだ。そして、孤独を恐れなくなった私は、いつの間にかいじめの対象から外されるようになり、孤独を恐れる別な子が、生け贄にされていた。私は、そんな醜いゲームとは関わりを絶った。それ以来、いじめというものに遭うことはなくなった。
協力や連帯は、社会の中で生きている以上必要なことだ。それを否定するつもりはない。だが、「人間最後は独りだ」という覚悟を持っていないと、自立した人間として、生きていくことはできないと思う。
|